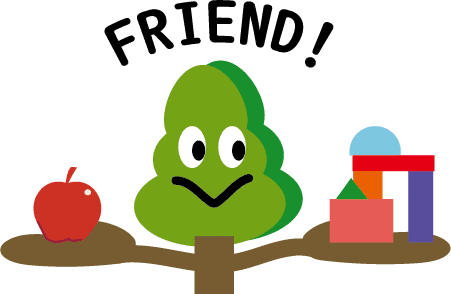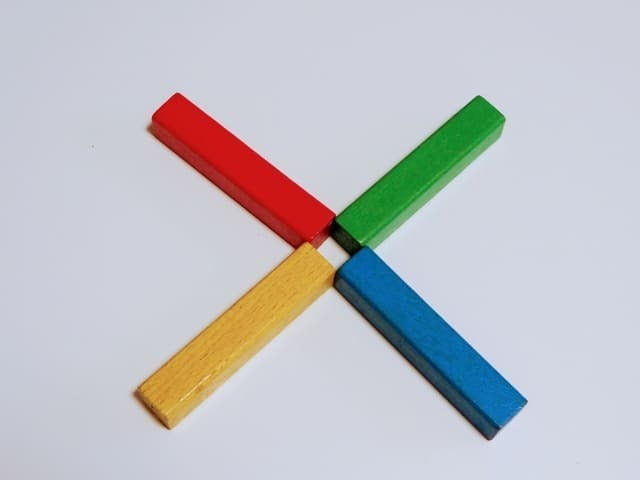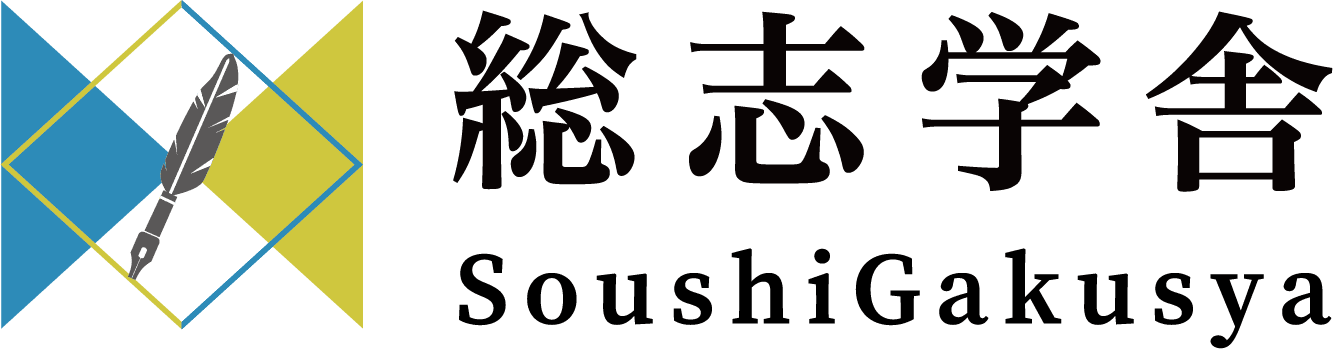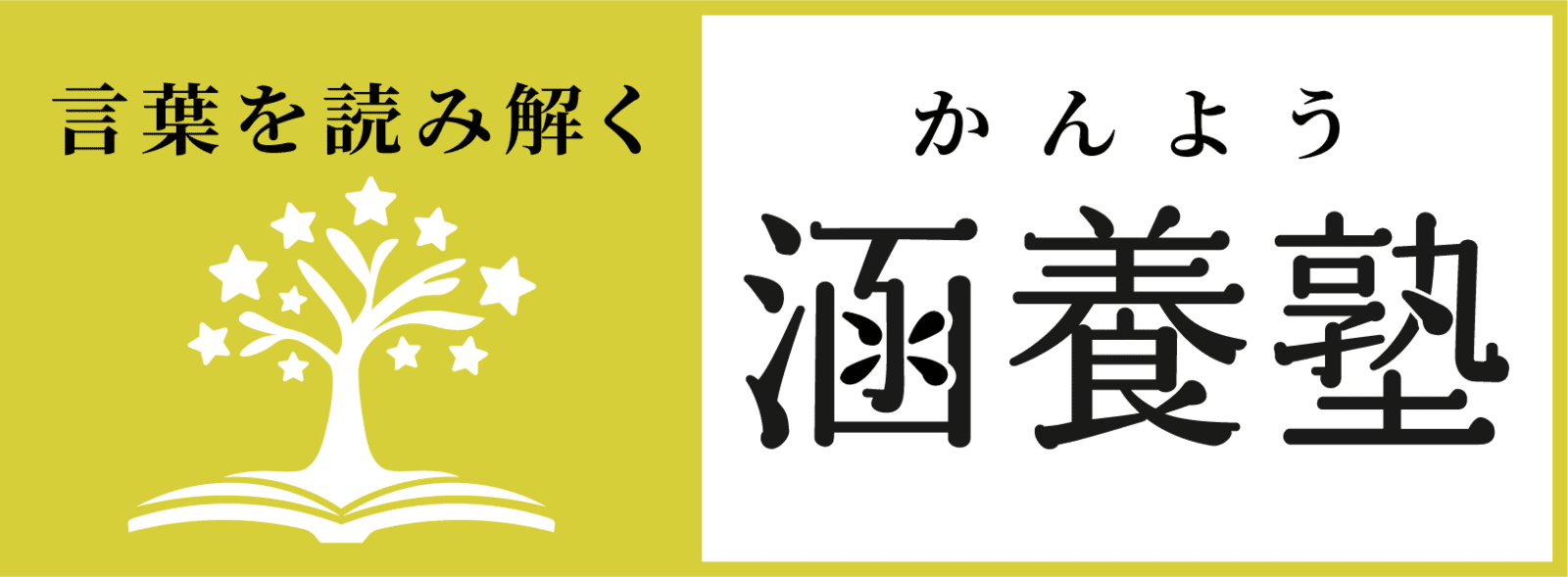1. この活動の狙い
物の浮き沈みの実験は、何のために行うのでしょうか。一般的なパターントレーニングでは、浮くもの沈むものをパターン化して覚えさせるために行います。 金属は沈む、木は浮く、土の下でとれた野菜は沈む等、確かに大切ですがそれだけだと少し物足りない。
2. ひらめき教室での実践例
そしてタイミングを見計らって、皆に問います。
「リンゴは浮くかな、沈むかな?」
私の実体験としてパターン化して覚えることに慣れている子の反応は決まっています。
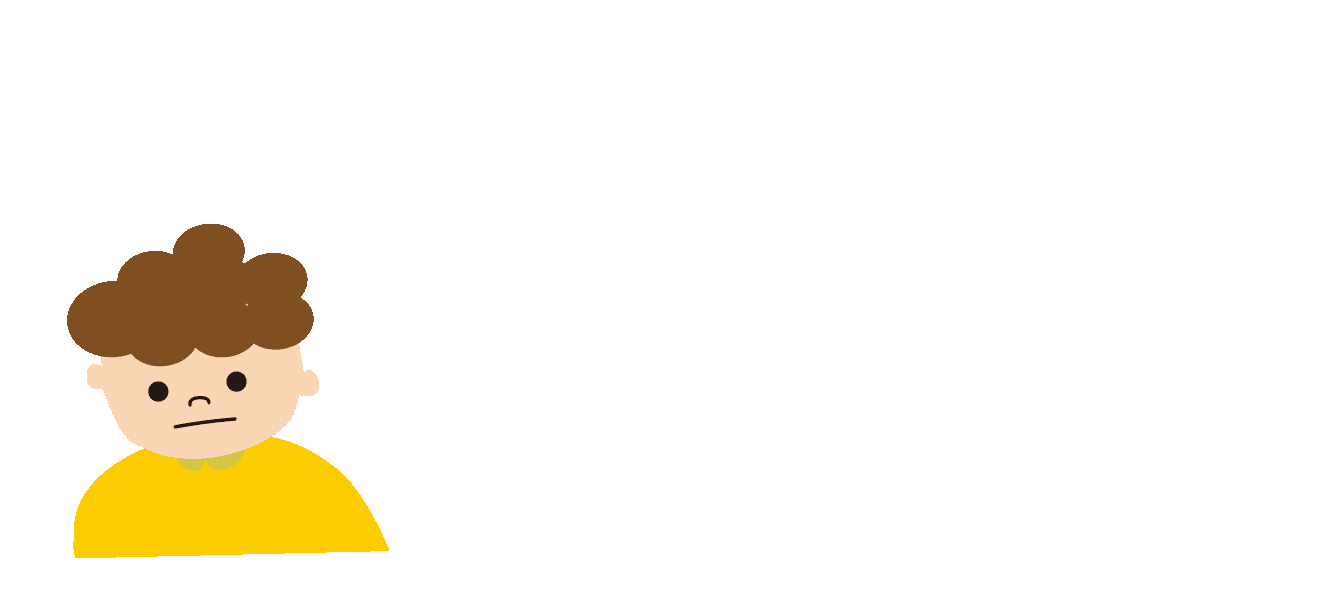
と恨めしげに見る。考えようとしない。 未知なる物への探求心が弱い。 ひらめき教室では、実際に物に触りながら実験を行った体験を生かし 心の声に耳を傾けながら子どもに発言させます。
子どもたち:
A:持ってみるとけっこう重いから沈む
B:でも、さっきのスイカは重くても浮いたから浮くんじゃない?
C:丸いじゃがいもは沈んだから、りんごも丸いから沈むと思う
自分の過去の経験が、未知のものにどうつながるのか考え始めています。
実際に水槽に入れると浮かびます。
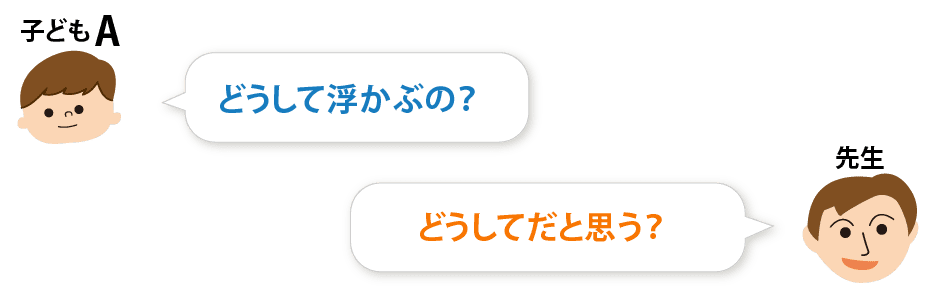
パターン化して覚えることに慣れている子の反応はやはり
子どもたち:
A:やったことがない。
B:知らない、わからない。
考えようとしない。そこでヒント。
先生:
リンゴってどこになっているか見たことある?
子どもたち:
家族でリンゴ狩りに行ったことがあるわ。木になっていたもの。
あ?
先生:
なにか気づいた?お話してごらん
子どもたち:
リンゴは木になるから、木は浮かぶからリンゴも浮かぶっていうこと?
リンゴと積み木は、見え方は全く違うが、実はどちらも木と仲良し、だから浮かぶことに気づいた見事な3段論法、まさに「③ひらめく」瞬間です。自分の経験を元にこの子は考えたのです。こんな子を育てたい。